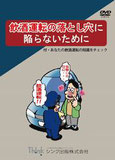■はじめに

昭和のドラマでよく見る場面があります。ヒロインがお父さんに彼氏を紹介しに行くと、「お前みたいな男に娘はやらん!」と激怒される。
すると大体の場合、かえって二人の愛が盛り上がってしまう。「いいんじゃない?」と歓迎されるよりも、「ダメだ!」と言われた方が、なぜか気持ちが盛り上がってしまうのです。ロミオとジュリエットの物語も、実はこの構造です。
この「禁止されると逆にやりたくなる」という心理現象は、私たちの日常生活の中に深く根ざしています。そして実は、安全教育や安全管理の現場でも重要な意味を持つ概念なのです。
■心理的リアクタンスとは
心理的リアクタンスは、1966年にアメリカの社会心理学者ジャック・W・ブレーム(Jack W. Brehm)によって提唱された理論です。
これは「自分の自由が制限されたり脅かされたりしたときに、その自由を回復しようとして生じる動機的な状態」と定義されています。
人間は本質的に自由でいたいと思っています。そのため、内容に関係なく「こうしなさい」「こうしてはいけない」と強く言われると、なんとなく気持ち悪くなって、つい逆のことをしたくなってしまう特徴があります。
もちろん個人差はありますし、内容によっても反応の強さは変わりますが、この心理的な仕組みは多くの人に共通して存在しています。
■安全との関わり

2018年初め、アメリカで奇妙なブームが起きました。P&G社の固形洗剤「タイド・ポッド」を食べる"洗剤食いチャレンジ"が若者の間で広がったのです。
事態を重く見た同社は、有名アメリカンフットボール選手を起用して「ノー、ノー、ノー」と洗剤を食べてはいけないと訴える動画を制作しました。
しかし、この呼びかけは逆効果となりました。動画公開から2週間足らずで、洗剤を飲んで病院に運ばれる人が倍増し、数カ月後には過去2年間の合計件数の2倍にまで急増したのです。
この事例が示すように、心理的リアクタンスは安全に直接的な影響を与える可能性があります。
道路交通法をはじめ、多くの安全規則は「こうしてはいけない」「こうしなさい」という指示の形で作られています。法律である以上仕方がない部分もありますが、安全教育まで「ああしろ」「こうしろ」ばかりになってしまうと、かえって反発を招くリスクがあります。
産業安全、医療安全、交通安全など、あらゆる安全領域において、上から目線の命令的な指導は「やらされている感」を生み出し、心理的リアクタンスを引き起こす可能性があります。
これは安全確保にとって逆効果となってしまいます。
■事例と実践

心理的リアクタンスを理解した安全教育では、「悪いことを減らす」だけでなく「良いことを増やす」アプローチが重要になります。
最近の安全研究、特に心理学の分野では、この前向きな安全の考え方がよく取り上げられています。
具体的には、「やらされている」状態から「自分からやりたくなる」状態への転換を目指します。
「こうしなければならない」ではなく、「こうすることで得られるメリット」を伝える。「ルールだから」ではなく、「安全のためにプライドを持ってやっているんだ」という気持ちを育てる。
例えば、安全装備の着用について「着用義務があるから」と強制するのではなく、「プロとしての誇りを示すもの」「仲間を守るための行動」として位置づける。
ヒヤリハット報告についても「報告しなければならない」ではなく、「チーム全体の安全向上への貢献」として価値を伝える。
このように、心理的リアクタンスを避けながら、自発的な安全行動を促進する教育手法を取り入れることで、より効果的な安全管理が可能になります。
強制ではなく、内発的な動機に基づいた安全文化の構築こそが、真の安全確保につながるのです。
執筆:島崎 敢 近畿大学助教授
 シンク出版
シンク出版