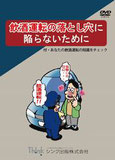■はじめに

心理的安全性は、最近とても注目されている概念です。きっかけはGoogleのプロジェクト・アリストテレスという研究でした。
Googleという巨大企業は世界中に散らばるたくさんのチームにできるだけ高いパフォーマンスを発揮してもらいたい。そこでチームがどのくらい効果的に仕事ができているか(Team effectiveness)と、心理学の知見から働く時間などの物理量まで、思いつく限り250個ほどの変数の相関を取ってみたのです。
そうしたら、なんと心理的安全性がトップになったのです。それ以来、心理的安全性はチームパフォーマンスに最も大きな影響を与える概念として一気に注目されるようになったのです。
■心理的安全性とは
心理的安全性は、ハーバード・ビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授が1999年に提唱した概念です。彼女の定義によると「対人関係のリスクを取っても安全であるという、チーム内で共有された信念」とされています。
つまり、チームの中で質問をしたり、ミスを報告したり、新しいアイデアを提案したりしても、批判されたり罰せられたりしないという安心感が共有されている状態のことです。
■心理的安全性と安全の関わり

不安があると、人は黙る方向に行ってしまいます。質問をすると「無知だと思われる」「馬鹿だと思われる」という不安から発言を控える。
新しいアイデアも「面倒だと思われそう」で言い出せない。ミスをしても「怒られるかも」と隠そうとする。「これ危ないんじゃないか」という気づきも、周りの目が気になって言えない。
しかし心理的安全性が高い環境では、自分をよく見せようとする必要がありません。「これちょっと危なそうです」「このやり方、改善しませんか」「やり方がわからないので教えてください」「すみません、ミスしたので一緒に改善策を考えましょう」といったことが素直に言えるようになります。
これにより、致命的な問題が早期に指摘されるようになります。航空機事故の歴史を振り返ると、心理的安全性の低さが原因と思われる事故が実際に多く存在します。
心理的安全性が低いために副操縦士が機長に燃料不足を言い出せず、その間に墜落してしまうといった事例が代表例です。
現場の安全管理においても、ミスを報告しない、やり方がわからないのに聞かない、といった状況はよくありません。心理的安全性が低いチームでは、ハイリスクな状況がそのままになってしまう危険性があるのです。
■事例と実践

エドモンドソン教授は、心理的安全性を高めるための具体的な方法をいくつか提示しています。
まず「困難な仕事に取り組んでいる」ことを常にリーダーが伝える。「私たちは困難な課題に挑戦しているので、みんなのアイデアを結集する必要がある」と言い続けることです。
次に「人間は間違いを起こすもの」だと認める。「私も含めて間違いはあるから、どんどん発言してください。間違っていてもいい」という姿勢を示すことです。
そして何か発言があったときは常に感謝を示す。たとえその指摘が間違っていても、「言ってくれてありがとう」「おかげで前に進めた」という態度を貫くことが重要です。
安全に関わる現場では、この「困難な課題」ということを言いやすい環境でもあります。長時間無事故で作業を継続することは、実際には非常に高度で困難な仕事です。
産業現場や輸送業など、様々な現場でリスクを低いレベルに抑え続ける安全確保は、決して簡単なことではありません。
この共通認識を持ち、「安全のための仕事はチーム全員で取り組むもの」「何か気づいたらすぐに教えてほしい」「それはとても価値があることだ」という雰囲気を作ることで、より安全な職場環境を実現できるのです。
執筆:島崎 敢 近畿大学助教授
 シンク出版
シンク出版