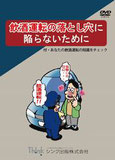■はじめに
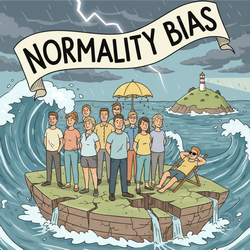
正常性バイアスは、災害時の避難行動を考える上で非常に重要な概念です。
なぜ避難指示が出ているのに人々は避難しようとしないのか。なぜ危険が迫っているのに対策を怠ってしまうのか。こうした疑問に答える鍵となるのが正常性バイアスです。
正常性バイアスとは、危機的な状況に直面したときに、その異常事態を正常の範囲内として捉えようとする心理的傾向のことです。
これは心理学における防衛機制の一種と考えられています。私たちの心は、危機的な状況が生み出す強いストレスから自分自身を守るために、「これは本当 の危機ではない」「自分の勘違いだ」と思い込もうとする傾向があるのです。
「今自分が危機的な状況にある」という認識は非常に大きなストレスとなるため、心は無意識のうちにそのストレスを軽減しようとします。
■正常性バイアスと安全との関わり

正常性バイアスは、災害時だけでなく、様々な場面で人々が逃げ遅れたり、対策を怠ったりする原因となります。
例えば、非常ベルが鳴った状況を想像してみてください。非常ベルの誤報は実際によくあります。火事かもしれないし、そうでないかもしれない。「前もこんなことあったな」と思うでしょう。しかしこれには、実は「そう思いたい」という心理が働いているのです。
もし本当に火事であれば、すぐに逃げなければなりません。今現在、自分が危機的な状況に置かれており、適切な行動をすれば助かるが、そうでなければ助からないという状況は、非常に大きなストレスです。そのストレスを避けたいがために、私たちは無意識のうちに「そうではない理由」を探してしまうのです。
過去の経験から「前も誤報だった」と考えたり、「先生が待機していいと言っている」といった権威者の指示を手がかりにしたり、周りの人を見て「まだ誰も慌てていない」と判断したりします。
正常性バイアスに関する実験も行われています。待合室に無害な煙を送り込むという実験では、興味深い結果が出ています。待合室に複数の人がいる場合、一人しか居ない時よりも逃げ始めるのが大幅に遅くなるのです。
複数人で待っている人は、お互いを観察します。そして「隣の人がまだ慌てていないこと」を手がかりにして、「大丈夫だ」と思い込もうとするのです。もしかしたら隣の人も、「まだ慌てていない自分」を見ているので慌てていないだけかもしれないのに。
災害時に考えると、警報が出ているのに「まだ大丈夫だろう」「隣の人も逃げ始めていない」「数年前の豪雨でも大丈夫だった」など、大丈夫な理由を探し、逃げ遅れが起きる。これが正常性バイアスによる深刻な影響です。
なお、正常性バイアスはパニックとちょうど逆の現象です。「災害時のパニックが怖い」と言う人もいますが、現実には災害でパニックが起きた例はほとんどなく、多くの人が正常性バイアスに陥るのです。
パニックが起きるためには、「競争に負けた人は助からない(損をする)」という条件が必要です。買い占めや銀行倒産の噂などはこの条件が当てはまりますが、災害からの避難は、安全な場所が人で埋め尽くされ、「競争に負けた人が助からない」という状況にはなりません。
逃げ遅れるのはまずいのですが、競争する必要がないので、パニックは起きないのです。
■危機的状況では「正常性バイアス」に囚われていないかを自己認識する

正常性バイアスへの対策として、まず重要なのは「自分にはそういう特徴がある」ということを知っておくことです。心理学的な傾向の多くがそうであるように、自分の心の働きを理解することが第一歩となります。
危機的な状況に直面したときは、「今、自分に正常性バイアスが働いていないか」と疑ってみることが大切です。この自己認識が、適切な判断と行動につながります。
「きっと大丈夫」と思い込もうとして人にも、「もしかしたら」という気持ちはあるので、「大丈夫ではないサイン」をキャッチすると正常性バイアスが破られます。
例えば集団の中の誰か一人が慌てて逃げ始めると、みんなが一斉にその人についていくのはこのためです。ですからこれを読んで正常性バイアスを知っている方は、是非「率先避難者」になってください。
「率先避難者」は全員である必要はありません。人口の5〜10%程度が正常性バイアスを自覚し、「とりあえず逃げておこう」というマインドを持って逃げ始めれば、その街や集団全体のリスクを下げることができます。
執筆:島崎 敢 近畿大学准教授
 シンク出版
シンク出版