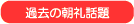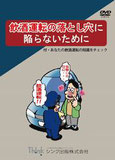酒を飲んでいるときには、飲めば飲むほど酔いが回っていくような感じがしますが、飲むことをやめて少し時間が経てば、酔いがすでに覚めているような錯覚にとらわれます。この感覚は、お酒を飲む人なら理解していただけると思います。
しかし、実際には自分が思っている以上にアルコールが残っていることが、いろいろな実験でも明らかにされています。
川崎医療福祉大学の金光先生らのグループは、14名の被験者に500ml缶のビール3本を飲んでもらい、30分後と3時間後に酔いの自覚を答えてもらう実験をしています。
30分後の酔いの自覚を聞いてみると、ほとんどの人が「とても酔っている」「まあまあ酔っている」と答えていますが、3時間後に聞くと14名中9名が「酔っていない」と答えていました。
ところが、実際のアルコール濃度を確認したところ、13名が酒気帯び運転の基準値である呼気中アルコール濃度0.15mlのラインを超えていました。
つまり、酔いが覚めていく過程では、アルコールの影響が残っていても過小評価されやすいことを示しているのです。
皆さんもご存じのように、アルコールは短時間では抜けないのですが、われわれの感覚は時間がたつと抜けたような錯覚に陥りやすいところに「飲酒運転の落とし穴」があります。
(シンク出版株式会社 2012.12.5更新)
運行管理者・配車担当者のためのスケジュール手帳
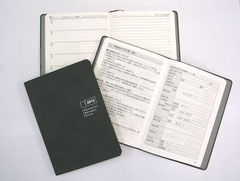
本手帳は、資料ページにトラックの運行管理者として知っておきたい知識を「法令編」「知識編」「データ編」にまとめ、一冊に収録しています。
また、週間カレンダーには安全スローガンを収録し、メモ帳も充実の内容でスケジュール管理も万全です。
カバーは高級感のあるビニールレザーを採用し、デザイン性も優れていますので、年末年始の贈答品としても最適です。
 シンク出版
シンク出版