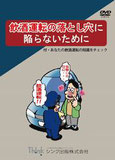先日、弊社の従業員が信号待ちをしていたところ、高齢のドライバ―が運転する軽自動車に追突されました。しかしながら、加害者である高齢者は無職で、任意保険に加入しておらず、物損事故の被害額を支払う能力がありません。このような場合、弊社としてはどのような対応をすれば良いのでしょうか?
■今回の事故の問題点

交通事故被害が生じた場合、本来であれば加害者が被害者に対し、生じた損害を賠償する責任があります。しかし、加害者が任意保険に入っておらず、資力もないというような場合には、事実上損害の賠償をすることができないことがあります。
この点、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は強制加入とされていますが、加入していないような場合もありえますし、加入していてもその補償の対象は人身事故による対人損害賠償であり、物損事故では適用されません。
その他交通事故で加害者に対する措置で考えられるのは、免許停止や取消等の行政処分や、人身事故の場合には刑事事件として立件され、処罰されることなども考えられますが、行政処分や刑罰は、あくまでも加害者に対する手続であり、実際に被害者が被った金銭的な損害が填補されるようなものではありません。
そのため、交通事故で生じた被害者の損害が賠償されず、被害者自身が負担しなければならないことがあります。
■損害保険の利用を検討
このような場合に備えて、特に運送業者等、業務として自動車を利用するような事業主は、まずは自身で損害保険に加入しておく必要があります。
単に人身傷害等に関するものだけではなく、物的損害についても対応できるように、車両保険や、運送貨物等が損害を受けた時に損害を填補できるような保険など、その内容を確認して加入しておくべきです。
■加害者に対する損害賠償請求

1・加害者に対する請求
この点、自ら損害保険等に加入していない場合には、その他の損害の回収方法を検討する必要があります。
しかし加害者が無保険・無資力である交通事故の場合、特に物的損害については、人身傷害に関する自賠責保険などのように利用できる制度や手続等は用意されていないといえます。
そのため、相手に対して通常の損害賠償請求等の方法により、損害の回収を図るということになります。
この場合、まずは直接相手に対して任意で請求して交渉する手段が考えられますが、相手が任意の支払交渉に応じてこないような場合には、民事訴訟を提起することを検討します。
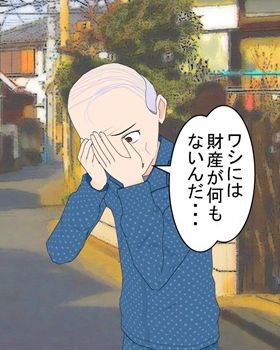
2・民事訴訟のポイント
交通事故においては、交通事故が生じた場合に通常の運転者が行うべき義務として警察に通報することが必要です。
通報して警察の実況見分などの捜査が行われていれば、被害者が事故態様や損害の立証を行うことは比較的容易であり、また質問の事例のように停止中に後ろから追突されたような、明らかに相手に過失がある場合には、相手も争わないことが多いため、損害額や因果関係も明確であれば、訴訟は長引かないで判決が出されることも考えられます。
なお、訴訟を提起したからといって、必ず判決が出るわけではなく、裁判所においてお互い協議をして和解をすることで解決する場合もあります。
任意の交渉を拒否していた相手が、訴訟においては裁判所に勧められるなどして、訴訟上の和解に応じ、合意ができることもあります。
ちなみに任意の交渉や訴訟上の和解による場合、双方が承諾していれば、分割払いの合意や、連帯保証人を付する合意(当然その連帯保証人も合意する必要がありますが)などができるため、判決が出された場合よりも柔軟な解決ができることもあります。
また、訴訟を提起しても相手が裁判に出て来ないこともあります。しかしこちらが適切に主張・立証を行っていれば、その場合でも判決を取得することができます。
この場合裁判所は、裁判に出頭しないという相手の態度について、本件について争わないものと判断し、当方の請求を認めるという判決を行うことになります。

3・判決後の対応
加害者に対し、被害者に対して金銭を支払うよう命じる判決が出ても、それだけで具体的に損害金が回収出来るわけではありません。
その判決を基に、再度相手に対して支払を請求することが考えられますし、応じないような相手に対しては、裁判所に申し立てて、相手の財産に対して強制執行の手続きをすることが考えられます。
強制執行をする場合、差し押さえなどの対象となる相手の財産はこちらが指定しないとならないため、財産の在処がわからない場合などは、さらに別に財産開示の請求手続をすることも考えられます。
しかし、財産がどこにもないような相手の場合には、結局回収ができず、被害が補填されないどころか、さらに弁護士費用等の費用までかかることもあります。
民事訴訟を考える場合には、このような回収できないリスクと、和解等も含めた解決の可能性などを慎重に考える必要があります。
■まとめ
被害者が会社の場合、種々の手段を講じても生じた損害が回収できない場合には、回収不能として税務上の損金処理を行うことになると思われます。
以上のとおり、相手方が無保険・無資力の場合の物的損害については、実際に回収ができない可能性が高いといわざるをえません。

執筆 清水伸賢弁護士
■WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!
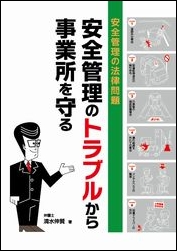
No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)
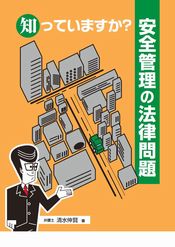
No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版