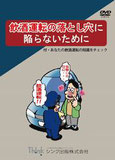先日、退社が遅くなりマイカーで帰宅中、点滅信号交差点に差し掛かりました。自車は黄色点滅信号だったので、注意しながら進行したところ、赤色点滅信号を無視して一時停止しなかった交差車両が、自車の前部に衝突する事故を起こしました。赤色の点滅信号を無視した運転者は、私を散々に非難して、警察が到着する前にその場を離れてしまいました。このような場合、現場を離れた運転者はどのような罪に問われますか?
■点滅信号の役割

信号機の表示する信号の意味や、その他信号機について必要な事項は、道路交通法4条4項で、政令によって定めるとされており、それを受けた道路交通法施行令2条1項に、信号機の表示する信号の種類や意味が規定されています。
同条同項によれば、まず黄色の点滅信号(黄色の灯火の点滅)は、歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができることを示しているとされています。
また、赤色の点滅信号(赤色の灯火の点滅)については、歩行者等と車両等では違いがあり、まず歩行者等は、黄色の点滅同様、他の交通に注意して進行することができるとされています。
他方、車両等は、停止位置において一時停止しなければならないとされています。
点滅信号は、早朝や夜間など交通量の少ない場所によくみられるもので、交通量が少ないのに通常の信号機で対応すると、却って交通量を阻害すると考えられることから設置されています。
しかし、点滅信号の意味を理解していない運転者もおり、赤色の点滅信号で一時停止しなかったり、黄色の点滅信号ならこちらが優先だとして、全く安全確認を行わないまま走行したりする運転者もいます。
中には「点滅信号の交差点は交通量が少ないから注意する必要がない」などと誤った考えの下で運転して、事故を起こす運転者もいます。
実際、点滅信号が設置されている交差点において出会い頭の事故が発生することはあり、点滅信号の運用の見直しがされているところもあります。
■点滅信号無視は交通違反に問われる

質問の事例では、赤色の点滅信号を無視して走行してきたということですので、一時停止違反です。
点滅信号の交差点は、交通整理の行われていない交差点であるとされますので、赤色点滅信号によって一時停止が指定されているのにこれを無視したという形になるため、道路交通法43条の一時停止違反になります。
同条に違反する行為は、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処するとされています(同法119条1項5号)。
ただ、交通反則金制度により、反則金(普通車は7000円)を支払うことで罰則の適用を免れることができます。なお、違反点数は2点となっています。
■事故後の行動次第では罰せられる

ただ、原因はどうあれ、交通事故が生じた場合の運転者は、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」とされています(道路交通法72条1項前段)。
また、当該車両の運転者は警察官に対して、「当該事故が発生日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」とされています(同法同条同項後段)。
そして、同条に反する行為にはそれぞれ罰則の適用があります。
すなわち負傷者の救護義務や危険防止措置義務等に違反する場合には、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の適用があります(同法117条1項)。
さらに、人が死傷している場合、それが当該運転者の運転に起因する物である場合には10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります(同法同条2項)。
負傷者がおらず、危険防止措置等も必要ないような場合でも、警察官に対する報告義務を怠った場合には、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金とされます(同法119条1項17号)。
また、これらについては交通反則金制度の適用があるものではありません。
■まとめ
質問の事例では、以上のとおりその場を離れた運転者には、赤色点滅信号の無視による一時停止違反と、少なくとも報告義務違反が認められますので、それに応じた罰則等の適用があることになります。
車両等を運転する際には、各点滅信号や道路標識等の意味内容を理解した上で安全確認を怠らずに運転する必要があり、万一交通事故が生じた場合には、運転者に課せられた各義務を果たし、間違っても報告等もせずにその場を離れるようなことがないようにしてください。

執筆 清水伸賢弁護士
■WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!

No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)

No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版