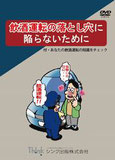先日、弊社の従業員が営業の帰りに高速道路で追突事故に遭いました。従業員は渋滞の後尾でハザードランプを点灯させ、停止するためにゆっくりと走行していたのですが、後続車両に追突され、車両は大破し、従業員も大けがを負いました。このような場合に、こちらの従業員に何かしらの責任はあるのでしょうか?
■一般道における追突事故

一般道路は、人や車両、自転車などいろいろな通行者が混在して走行・歩行することが想定されています。
道路交通法等も、それらの接触等の危険を回避することを中心に考えられており、事故が生じた際の過失割合の判断も、そのような視点に基づいて行われます。
一般道における追突事故の場合には、被追突車(追突された車)が急ブレーキをかけるなどの過失もなく、例えば赤信号で停止をしていたところを追突されたなどの場合には、その過失割合は追突車(追突した車)が100、被追突車が0となります。追突車には前方不注視や車間距離不保持の過失があるといえ、それが原因となっていると考えられるためです。
なお、被追突車が急ブレーキなどをかけた場合でも、基本的には追突車の前方不注視や車間距離不保持の過失は存在すると考えられるため、追突車と被追突車の基本的な過失割合は、70対30とされています。
ただし、道路交通法24条は、「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」とされています。
つまり、被追突車が急ブレーキをかけたのが危険を防止するためやむを得ない場合であれば、その過失割合は追突車が80で、被追突車が20程度になると考えられます。
■高速道路上における追突事故

一方、高速道路においては、二輪車は含むものの、基本的には自動車のみの通行を想定している道路であり、一般道路よりも高速での走行が許容されていることから、高速走行を行うことのできる環境を維持しつつ、自動車の安全かつ円滑な走行を確保することが重視されているといえます。
高速道路上では、最低速度が定められ(法75条の4)、法令の規定や警察官の命令、あるいは危険を防止するため一時停止する場合、その他駐車スペースや料金の支払時、故障等やむを得ない場合の十分な幅員のある路肩等への駐停車など以外には、停車し、又は駐車してはならないとされます(法75条の8)。
また高速道路上における追突事故の場合、被追突車に過失がなく減速または停止等をしていた場合には、追突車と被追突車の過失割合は100対0であり、変わりませんが、基本的には禁止されている駐停車を被追突車が行ったことについて過失が認められるような場合、追突車と被追突車の過失割合は、基本的に60対40と考えられます。
さらに高速道路において故障などのやむを得ない理由により本線等や本線等に接する路肩や路側帯で当該自動車を停車せざるをえなくなった場合には、運転者は当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならないとされています(法75条の11第1項)。
また運転者は、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない(同第2項)とされています。
そのため、駐停車したこと自体に過失が認められないような場合でも(例えば自分に過失がないような形の先行事故のため停車せざるを得ない場合など)、停車後に退避措置や後続車に対する停止表示器材の設置などの適切な行為を行わなかった場合には、その過失割合は80対20が基本とされます。
■渋滞による減速・停止の際の一般的な対応はマナーの範疇

ただ、質問のように高速道路上において渋滞が生じている場合には、停車後に退避させたり、停止表示器材を設置したりすることはできません。
また、高速道路上で渋滞により減速や停止をする際には、後方を確認した上で、後続車に知らせるためにポンピングブレーキによって減速したり、ハザードランプを点灯させたりすることが一般的ですが、これらのポンピングブレーキやハザードランプの点灯は、法律で定められた義務ではなく、マナーの範疇を超えるものではありません。
もちろん、渋滞により減速・停車する際にはこれらの行為をするべきといえます。
しかしながら、被追突車が急ブレーキで減速・停車などの危険な走行をしていない限り、これらの行為をしていなかったことが直ちに過失とされることは考えにくいといえ、やはり追突車の前方不注視や車間距離不保持の過失が事故の発生原因ということになるでしょう。
■質問の場合の過失割合
質問の事例では、被追突車は、上記の対応もしていますし、急ブレーキなどの危険な走行をしていたわけでもありません。
そのため、追突車と被追突車との過失割合は、100対0になると考えられ、運転をしていた従業員には責任は生じないと考えられます。

執筆 清水伸賢弁護士
■WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!
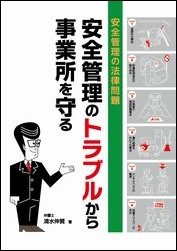
No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)
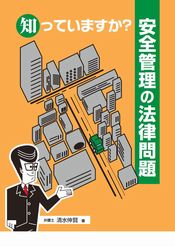
No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版