
弊社は電化製品の卸会社で、運送会社に商品を運んでもらっています。2024年4月よりトラックドライバ―にも働き方改革の一環で、改善基準告示が強化されました。そのころから、「トラックGメン」という聞きなれない言葉を耳にするようになりました。「トラックGメン」は荷主の元を訪れて、ドライバーの負担を軽減するように指導しているようですが、荷主が指示に従わなければ罰則などが適用されるのでしょうか?
■2024年問題による物流業界の変化

2019年4月にから、いわゆる働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に基づく労働基準法や労働安全衛生法等、関連する種々の法律の改正)が順次施行されました。
2024年4月からは、猶予期間が設けられていた貨物運送事業者等の業種にも時間外労働の上限規制等が適用されており、それに併せて改善基準告示も改定されています。
いわゆる2024年問題といわれているものですが、法や改善基準告示などに従わない(あるいは従えない)業者もまだまだみられるようです。
■「トラックGメン」とは

・貨物自動車運送事業法による荷主に対する規制
貨物自動車運送事業法附則第1条2の1項では、国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が法律や法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(違反原因行為)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができるとされています。
また同条2項では、国土交通大臣がその荷主に対し、法律や法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができるとしています。
同条3項では、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができるとされています。
そして、同条4項では、荷主が要請を受けてもなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができるとし、同条5条でその勧告をしたときは、その旨を公表することも定められています。
また、同条7項では、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知することも定められています。

・「トラックGメン」の誕生にいたる経緯
このように、運送事業者の労働環境の改善を図るために、荷主の不当な要求や違反行為に対して是正指導を行うことを目的として、令和5年7月に発足したのが「トラックGメン」といわれる国土交通省の人員組織です。
なお、当初はトラック事業者を対象としていましたが、令和6年11月には、物流全体の適正化を図る観点から、「トラック・物流Gメン」に改組し、倉庫業者からの情報収集も行うことが広報されています。
同広報によれば、体制も拡充され、本省・地方運輸局等の物流担当部署から29名、各都道府県のトラック協会が新たに設ける166名の「Gメン調査員」を追加し、総勢360名規模となっているとのことです。

・Gメンの具体的な業務内容
「トラックGメン(トラック・物流Gメン)」は、主に違反原因行為の情報を収集します。
すなわち、長時間の荷待ち、過積載の依頼、無理な到着時間の設定や異常気象時の無理な運行指示、依頼にない附帯作業を行わせたり、運賃や料金を不当に据置きしたり、ドライバーの拘束時間超過などがないかを調査します。
第三者やドライバーからの通報を受けて調査を行うことも多くあります。
そして、違反原因行為があった場合には、荷主に対して是正の指導を行います。同指導には、その内容や程度に応じ、ヒアリングなどを通じた事実上の働きかけ、要請、勧告及び公表と段階があり、指導を受けた荷主には、その問題点を解消することが求められます。
荷主が違反原因行為をしている疑いがあると認められる場合には働きかけがあり、働きかけをしても改善されないなど荷主が違反原因行為をしていることを疑う相当な理由がある場合は要請、要請をされてもなお改善がなければ勧告及び公表、という段階を踏むことになります。
■指導に従わない場合は……
このように、是正指導に従わない場合には、最終的には勧告及び公表となり、社会的信用に影響があります。
また、その違反態様において、貨物自動車運送事業法等の重大な違反の疑いがあるときは、行政処分の対象となることがあり、また、上記のように不公正な取引がある場合には公正取引委員会に通報されることがありますし、過積載の指示や、雇用関係にあるドライバーの違法な長時間労働など、各法規における罰則を伴う規定の違反行為の発覚の端緒ともなりえます。
現時点では、指導に従わなければすぐに罰則の適用があるというわけではありませんが、荷主や運送事業者としては、是正指導を受けないように現場の実態を把握し、事前に業務の効率化を図ったり、運賃の適正化行ったりすることが必要です。
また、是正指導を受けた場合には、その内容に従って対応することが求められます。

執筆 清水伸賢弁護士
WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!

No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)
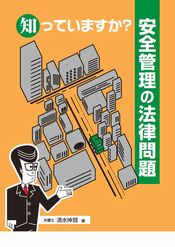
No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版















