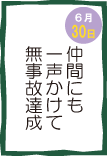横須賀市で発生した飲酒運転事故をはじめとして、京都市などでも飲酒が起因となる事故が発生しています。横須賀市の事故では同乗者が事故直後に現場から離れ、その後出頭した様ですが、このような飲酒運転の同乗者や、お酒を提供した飲食店も罰せられると聞きました。私どもは小さな居酒屋を営んでいるのですが、飲酒運転のほう助に問われないために、どのような対策をすれば良いでしょうか?
■法律における飲酒運転の罰則

道路交通法上、運転者に対する罰則が定められている飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。
「酒気帯び運転」は、同法65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されており、具体的には呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転を行うものです。
「酒気帯び運転」を行った場合、行政処分としては呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満の場合は13点減点で免許停止期間90日、0.25mg以であれば25点減点で免許取消(欠格期間2年)とされています。
また、罰則(刑事処分)として、「酒気帯び運転」をした運転者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています(同法117条の2の2第1項第3号・なお、懲役刑は令和7年6月1日から禁固刑とともにいずれも拘禁刑として一本化されますが、本稿では施行前ですので従前どおり懲役刑と表記します)。
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます(同法117条の2第1項第1号)。
呼気中のアルコール濃度の値にかかわらず、アルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしているような状態であり、顔の紅潮や目の充血、日時や場所などを正しく認識できなかったり、呂律が回らなかったり、警察官とのやり取りがうまくできないような状態、片足立ちや真っ直ぐ歩くことができないなど、正常な運転ができない状態であると判断されれば、「酒酔い運転」とされます。
「酒酔い運転」に対する行政処分は、35点の減点で免許取消(欠格期間3年)であり、罰則(刑事処分)としても、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(同法117条の2第1項第1号)。
「酒気帯び運転」に比べると「酒酔い運転」の方が罰則等は重くなっていますが、運転者の状況によっては、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満でも「酒酔い運転」とされることがありますので注意が必要です。
また、自転車も「車両等」であり(軽車両)、飲酒運転をしてはならないとされています。
■飲酒運転者以外の者への罰則
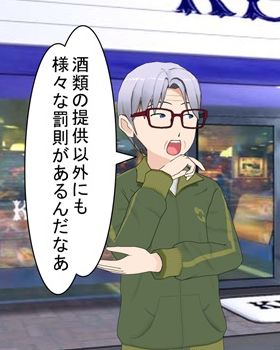
飲酒運転について、以前は運転者だけを処罰の対象としていましたが、平成19年9月19日に施行された改正道路交通法により、飲酒運転をした運転者だけではなく、運転者に車両を提供した者や、お酒を提供した者、そして飲酒運転の同乗者に対しても、規制の対象となり、それぞれ罰則が定められています。
これらの罪は、本来は飲酒運転の幇助犯(ほうじょはん)といえる行為であったものを、それぞれ定型化して独立に定めたものです。
また、これらの罪を行った際、相手の運転者が、自動車運転過失致死傷罪や、危険運転致死傷罪を犯せば、場合によっては提供者や同乗者にも別途それらの罪の幇助犯が成立することもありえるので、注意すべきです。
各罰則の詳細については、以下の通りです。
・車両提供罪
車両提供罪は、同法65条2項で「何人も、酒気を帯びている者で、前項(同条1項)の規程に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。」とされており、違反した場合の罰則は、運転者が「酒酔い運転」をした場合には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされます(同法117条の2第1項第2号)。
・酒類提供罪
酒類提供罪として同法65条3項は、「何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」としています。
提供者は飲食店も含まれますが、本罪が成立するためには酒類の提供を受ける者等が車両を運転することとなるおそれがあるという認識を有していなければならないとされています。
また、本罪が成立するためには、提供者が酒類を実際に提供したこと、実際に車両が運転されたこと、運転者に「酒気帯び運転」ないし「酒酔い運転」等が成立することが必要です。
同罪の罰則は、運転者が「酒酔い運転」をした場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法117条2の2第1項第5号)、「酒気帯び運転」をした場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法117条の3の2第2号)とされています。
・飲酒運転車への同乗罪
そして同法65条4項はいわゆる同乗罪として、何人も、車両の運転者が「酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送するよう要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(注:酒気帯び運転禁止の規定)に違反して運転する車両に同乗してはならない。」とされています。
同乗罪は、運転者が「酒酔い運転」をした場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法117条2の2第1項第6号)、酒気帯び運転をした場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(同法117条の3の2第3号)とされています。
■酒類提供罪に問われないために行うべき対策

質問のような飲食店の場合に、酒類提供罪に問われないためには、端的にいえば、飲酒運転を行うと思われる顧客に対して酒類を出さないという対応が必要です。
まずは顧客の来店時や最初のオーダー時(遅くとも飲食を提供する前)に、必ず運転して帰宅するかどうかを確認することが必要です。
飲酒運転の対象は自転車も含まれ、罰則がありますので、自転車も含めて運転して帰宅する人がいるかどうかを確認し、もしいればその人に対しては酒類の提供を拒否しなければなりません。
顧客がグループで来店していた場合には、ハンドルキーパーが誰かを明確にしてもらい、酒類の提供をしないように注意することが必要です。
その他、アルコールとソフトドリンクの区別がつけられるようにグラス等を変えておき、誤って酒類を提供しないような措置をしたり、店内にハンドルキーパー運動や飲酒運転防止の掲示をしたり、タクシーや運転代行の案内や、最寄り駅の終電時間の掲示をするなど、運転をしないで帰宅できるような案内を掲げることも有用でしょう。
さらに、アルコールチェッカーなどを備えて退店時に確認してもらうことができれば、飲酒運転の防止が一層図られることになります。
酒類を提供した顧客が帰宅する際に、運転することが分かったような場合には、飲食店としては運転をせず、家族などに迎えに来て貰うなど他の方法を挙げて説得し、場合によっては110番通報を行うことも考えられます。それを前提として、店内に110番通報することがある旨を掲示しておくことも良いかもしれません。
もちろん、物理的にも費用的にも、以上のような対策を全て講じることが困難な場合もあるでしょうし、以上の対策を全て講じておかなければ必ず酒類提供罪が成立するというわけではありません。
ただし、飲食店としては最低限、酒類の提供をするにあたっては、顧客に対して運転をしないことを確認しておく必要はあるといえます。
確認しても運転者が嘘をつくようなこともあるかもしれませんが、必要な確認を行った上で嘘によって騙されたというのであれば、飲食店側に酒類提供罪が成立する可能性は低くなるといえるでしょう。
いずれにせよ、飲酒と運転は出来る限り切り離させるような対応を行うことが必要です。

執筆 清水伸賢弁護士
■WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!
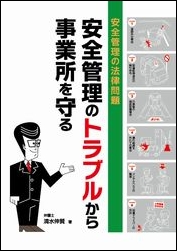
No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)
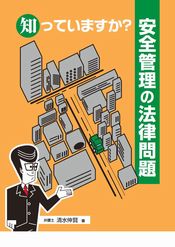
No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版