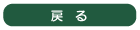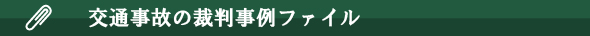
このコーナーでは、管理者や運転者が知っておきたい交通事故の裁判事例について、わかりやすく紹介しています。
◆連続事故における共同不法行為責任の過失相殺(2023年7月3日更新)
◆左折レーンから直進した車の過失責任は大きい(2023年6月19日更新)
◆飲酒運転した車への同乗者に対する「ほう助」認定について(2023年6月1日更新)
◆速度超過したクルーズコントロール設定は、過失相殺の対象になる(2023年5月16日更新)
◆車両譲渡手続きの不備で、運行供用者責任を問われた例(2023年4月19日更新)
◆スマートフォンの運転中利用事故は重罰(2020年9月1日更新)
◆運転者から企業への事故の逆求償を認める(2020年4月2日更新)
◆あおり運転で「殺人罪」などの判決(2019年4月1日更新)
◆「ながらスマホ」の死亡事故に求刑を上回る判決(2019年2月1日更新)
◆健康起因事故の賠償責任を否定した裁判例(2018年11月1日更新)
◆「あおり運転の車に賠償請求権なし」とした裁判例(2018年9月3日更新)
◆ひき逃げは、重大な犯罪として追及されます!(2018年7月25日更新)
◆運転者に賠償額の求償をした裁判例(2018年7月2日更新)
◆過積載が死亡事故に結びついたと認定された裁判例(2018年5月1日更新)
※当サイトに掲載した交通事故の裁判事例情報は → こちらのページを参照
2023年
7月
18日
火
被害者が代表を務める会社の休業損害

今回は、幹線道路の側道から信号のある交差点を左折しようと横断歩道手前で歩行者等の横断を待って停止していた乗用車に、幹線道路から左折してきた貨物自動車が後方から衝突した事故で、乗用車運転者の通院加療などに関して運転者が代表取締役を務める会社の休業損害が争われた事例を紹介します。
ラーメン屋の主人など個人事業主の場合、実質的に被害者が休業すれば事業が停止するなどの影響があるので、事業の損害が認められる場合があります。
■小規模ではあるが、実質的に個人会社とまでは言えず、経済的同一性を否定
【事故の状況】
平成29年2月21日午後8時46分ごろ、Aは乗用車を運転して東西に走る幹線道路の側道から左折しようとし、左折先の横断歩道上の歩行者や自転車をやり過ごすために、横断歩道手前でほぼ停止していたところ、幹線道路から左折してきた貨物自動車Bに後方から追突されました。
Aは、この事故により頚部捻挫、腰部捻挫の障害を負い、3つの医療機関に計90日間通院し、通院による時間的拘束のため、Aが代表取締役をつとめる化粧品会社の業務に支障が生じたとして、実際に業務に支障が出たと考えられる22.5日分の休業損害34万1,876円をBに請求するのが相当であると主張しました。
一方Bは、Aが代表取締役をつとめる化粧品会社は3名の従業員がいる会社であり、実質的にAの個人会社ということはできず、また、Aと化粧品会社の経済的同一性についても立証されていないとし、さらに、事故によりAに生じた症状はいわゆるむち打ち症であり、医師から就労制限があったとされる証拠はないこと等から、化粧品会社の間接損害は認められないと主張しました。

【裁判所の判断】
この訴訟について裁判官は、
「事故当時、Aの化粧品会社には、3名の従業員が在籍し、うち1名はデザイナーであり、顧客の要望を前提に自身のオリジナリティーを発揮する仕事をしていることが認められる」
「上記の事情に照らせば、小規模ではあるが、実質的にAの個人会社ということはできず、また、Aと化粧品会社の経済的同一性があるとまでは認められない」
などとして、Aが代表取締役を務める化粧品会社の休業損害を認めませんでした。
 シンク出版
シンク出版