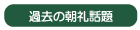黄信号で通過する習慣を見直そう - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

昨年2月、東京都大田区の交差点で乗用車が赤信号の横断歩道を渡っていた自転車の男性をはねて死亡させる事故があり、先日東京地裁で自動車運転処罰法違反(過失致死罪)に問われた乗用車の運転者に対して、無罪を言い渡す判決がありました。
乗用車は時速94キロで走行しており、交差点の約50m手前で信号が黄色に変わったのですが、そのまま直進を続けて自転車をはねたものです。
判決のなかで「直前の雨で道路がぬれ、急ブレーキをかけてもスリップする危険があった」と指摘したうえで、法定速度の60キロで走行しても事故は回避できなかった恐れがあるとしています。
確かに、黄信号で安全に停止できない場合には通過できると道路交通法に定められているのですが、運転者の行動を見ていると、初めから黄信号で通過しようとしていたのではないでしょうか。
最初は、安全に停止できなくて通過していても、それが習慣になるとかなり手前で黄色に変わっていても、安全に停止できないからと強引に通過するようになります。
このような行動が習慣化すると、すでに交差点手前で赤信号になっているにもかかわらず通過しようとします。
いくら裁判で無罪になっても死亡事故を起こしたことには変わりません。交差点手前では、スピードを出して通過するのではなく、黄信号に備えていつでも停止できるスピードで運転してください。
(シンク出版株式会社 2020.11.12更新)
■「鳥の視点」で運転席からは見えない危険を発見しよう

交差点事故を起こさないためには、運転席からは見えない危険を見つけ出すことが大切です。そうした危険を発見するには、運転席の上空から見る鳥のような視点を持って、交差点全体の交通場面をイメージする力(メタ認知能力)が必要となります。
新刊小冊子「交差点を鳥の目で視ると隠れた危険が見えてくる」では、交差点の6つの運転場面を提示して、隠れた危険をイメージできるかを考えるとともに、それぞれ俯瞰図で交差点の危険を見ながら解説を読んで理解する構成となっています。
メタ認知能力を高めるための教材としてもご利用いただけますので、ぜひ事業所での交差点事故防止教育にお役立てください。
 シンク出版
シンク出版